授業詳細
CLASS

民藝・柳宗悦が愛した「瀬戸本業窯」
800年の歴史散策と作陶体験
開催日時:2013年12月07日(土) 12時00分 ~ 15時50分
教室:①窯垣の小径(かまがきのこみ) ②瀬戸本業窯(せとほんぎょうかま)
レポートUP
先生:
水野 雄介 / 瀬戸本業窯・八代目水野半次郎 後継
カテゴリ:【ものづくり/くらし/瀬戸】
定 員 :30人
・雨天決行ですが、暴風雨の場合当日朝9時までにメールにてご連絡したします。
・文化財や伝統ある工房での体験になりますので、むやみに物に触らないようお願い致
します。
民藝運動をおこした柳宗悦、バーナード・リーチは世界中の「用の美」を求めて旅をして
いました。
近代化の中で、人々が求め続けていることは「人間と自然とモノの調和」。
いつも自分に問いかけています。
毎日を丁寧に暮らしたい。
ココロを豊かにするってどんなことだろう?
長い時を経て誠実に作られたモノが無言で教えてくれるのは、
自然への敬意だったり、人の生き方だったりします。
シンプルで研ぎ澄まされた使い易いモノの美しさにふれてみたい。
「無技巧とみえるまでの技巧」の美しさを好んだ白洲正子が愛した器を見てみたい・・・。
そんな思いからこの授業を作りました。
都会の喧騒を横目にして、のんびりと電車に揺られて名古屋栄から30分。
伝統にささえられてきた「かくれ里」での民藝陶器の作陶体験。
今回の特別授業の先生は、普段の暮らしぶりや人柄までも映し出される
誠実な陶工・水野半次郎八代目後継予定 水野雄介氏が
800年の間守り伝えられてきた大切な知恵と心のつまった歴史散策を案内し、
作陶を体験指導してくださいます。
焼物を知らなくても、食器が好きな人!
歴史は興味なくても、手しごとに興味がある人!
たくさんの「いいね!」を見つけに行きましょう!
※本業焼きとは、鎌倉時代から窯業の基本となったやきものを「本業焼き」を呼び、
1800年頃から始まった磁器製品を「新製焼」と言います。
【授業の流れ】
11:45 受付開始
12:00 授業スタート
授業の流れ説明&20秒自己紹介
教室までまち歩き
12:20 窯垣の小径入口で先生と合流
歴史さんぽ
13:00 瀬戸本業窯でやきもの授業
13:30 陶工の指導で作陶体験(ろくろ、釉薬かけ)
15:30 生徒さんからの質問
水野先生の挨拶
15:40 アンケート・集合写真
15:50 終了
(授業コーディネーター / 斎藤 貴子 (YUI)
本授業に関してのお問い合わせはこちらまで seto800@dnu.jp)
瀬戸散策や初めての作陶体験を楽しみに参加された方、趣味で陶芸を習っている方や陶器にとても強い関心がある方等、生徒さんそれぞれのワクワクした思いを持っての参加です。20秒自己紹介と、瀬戸の歴史のお話を聞きながら、皆さんの表情がすっかり柔らくなったところで、まち歩きスタートです。
向かった先は、銀座通り商店街とせと末広商店街。昭和30年代に設置されたアーケードがレトロな雰囲気を醸しだす商店街の様子に、生徒さんは興味津々。思い思いの言葉をキャッチボールしながら、楽しく会話が弾んでいます。晴天に恵まれ、木々の風景や頬を伝う風の冷たさに、時折冬の季節を感じながらも、あっという間に先生との待ち合わせ場所に到着しました。
窯垣の小径入り口で、私たちを温かく、優しい笑顔で迎えてくれたのは、水野雄介先生(瀬戸本業窯『水野半次郎』後継予定)です。水野先生は、江戸時代から続く窯元の8代目。その守り続けられてきた大切な知恵と、誠実なモノづくりの姿勢をそのままに、歴史散歩に連れて行ってくれました。
窯垣の小径は、タナイタ、ツク、エンゴロなどの窯道具で築かれた石垣、壁や塀が美しい約400メートルの散策路です。先生のわかりやすい説明を聞きながら、生徒さんの好奇心が喚起されます。洞町が、やきもののまち瀬戸の主力生産地であったこと。その昔、この小径こそがメインストリートで、窯場へ通う職人さんや、窯から出された製品が往来する洞町の産業を支えた道であったこと。そのような歴史を知ることで、目の前にある壁や塀のみごとさがより鮮明になります。「人々の生活と仕事の中から生まれてきた自然の景観であるからこそ、無作為の美しさがある」という水野先生の言葉が心に残りました。
次に向かったのは、窯垣の社。ここは、瀬戸最大級の登り窯の跡地で、少なくとも800年ほどの瀬戸のやきものの歴史が蓄積された土地だと考えられています。東ボラ窯跡では、下から眺めるだけではなく、斜面を登った上の方からその登り窯の大きさを体感しました。里山の山林の中で、かつてこの道を職人さんがあがってきたことを思うと、感慨を覚えます。
そんな歴史に思いを馳せる時間を経て、作陶体験を行う瀬戸本業窯に到着しました。
本業窯という呼び名は、1800年以降に磁器が焼かれるようになると、磁器を「新製」と称し、それ以前から生産していた陶器を「本業」と呼んで区別したことから始まりました。土も釉薬もその土地の原料を使用し、その土地の人々の暮らしの必要に応じて製作します。瀬戸本業窯は、今も昔と変わらずやきもの本来の姿を守り続けています。
隣接する瀬戸本業窯資料館で、民藝運動の推進者、柳宗悦、バーナード・リーチ、河合寛次朗、濱田庄司などに見出された瀬戸本業窯の歴史を興味深く学びました。水野先生のお話に聞き入る生徒さんの表情はみな熱心で、真剣で、そして楽しそう。瀬戸本業窯は、日常の食器として毎日の使用に耐える堅牢さを備えています。また、昔は3世代家族であったのに対し、今では核家族化が進み、家族構成の変化とともに生活様式も大きく変わりました。それに伴って、私たちの生活の中にある「器」も大きく変化しています。瀬戸本業窯は、昔から続いていることをただ守っているのではなく、昔から続いていることを守りながら、その時代背景に必要な実用食器をつくり続けてきたのです。
そして最後は、生徒さん待ちに待った作陶。水野先生と職人さんのご指導のもと、釉薬かけとろくろの体験です。「お椀より丸い感じ」「ビアグラスみたいなものが作りたい」「湯のみみたいな感じ」と、それぞれに作りたいモノのイメージを職人さんに伝えます。生徒さんの要望を的確にとらえ、アドバイスと手助けをしてくれる職人さん。職人さんと対面になってろくろに向かい、その形がつくられるまでの間の静寂感と生徒さんの真剣なまなざしが印象的です。そして、形づくられた瞬間の「わあー」「素敵、こんな感じです!」と生徒さんの喜びの声と満面の笑みで、それまでの緊張した空気がポンとはじけて消えました。
授業のしめくくりは、生徒さんからの質問タイムです。たくさんの熱心な質問に丁寧に答えてくれる水野先生。生徒さんの充足感にあふれるまなざしや、「若い人たちが憧れる存在になっていただきたい」という水野先生へのエールなどから、この授業の時間を共有したみなさんにとって充実した時間であったことがわかり、素晴らしい雰囲気でした。作品がみなさんのお手元に届く日が楽しみですね。
尾張瀬戸駅から歩いて行くことができる、伝統に支えられてきた「かくれ里」での民藝陶器の作陶体験。水野先生から、深い歴史、たくさんの気づきと豊かなモノの見方を教えて頂きました。平凡な日常生活の当たり前と思っていることの中にこそある幸せへの気づき。その気づきが、毎日を丁寧に暮らすことにつながり、心を豊かにしてくれるのだと思います。
(レポート:ボランティアスタッフ エリミ
カメラ:ボランティアスタッフ YUI)
この授業への皆さんからのコメント
作品が届くのを楽しみに待っているのですが、いつくらいに
発送されるものなのでしょうか?
自宅への送り状番号を控え忘れてきてしまい、発送確認ができない次第です。
まだ発送となっていないのであればよいのですが、参加してから3カ月たつためそろそろかなと思っております。
すでに発送されているようでしたら、問い合わせ先を教えて頂けましたら幸いです。
コメントを投稿するには、会員登録した後、ログインして頂く必要があります。
この授業への皆さんからのトラックバック
トラックバックがありません。トラックバック用URL
例)/subjects/trackback/226/a1b2c3d4e5
また、トラックバックは承認制のため表示に多少時間がかかります。
先生
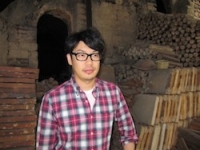
水野 雄介 / 瀬戸本業窯・八代目水野半次郎 後継
「本業焼きの歴史文化を守るために日々作陶している。」 歴史に新しいエッセンスを取り入れ、瀬戸本業窯や瀬戸焼を守る活動に尽力されています。 ■瀬戸本業窯HP■ http://www.seto-hongyo.jp/
今回の教室
①窯垣の小径(かまがきのこみ) ②瀬戸本業窯(せとほんぎょうかま)

住所:集合場所:名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅下車 となり「パルティせと」1階案内所前
《アクセスのご案内》
電車:名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅(栄から25分)
車:栄から40分ほど
 地図を見る
地図を見る
①窯垣の小径
エンゴロやタナイタなどの窯を焼く際に使用した窯道具を積み上げて築かれた幾何学模様
の壁や塀のある小径を散策できる。かつては、荷車や職人が行き来したメインストリートも
あり、やきものの街ならではの風情漂う光景によって往時を偲ぶことができる。沿道の「窯
垣の小径資料館」には、明治・大正期に一世を風靡した「本業タイル」で装飾した浴室や瀬
戸染付の便器が保存されており、洞町の歴史や文化の紹介をしている。
http://www.seto-marutto.info/cgi-bin/data/miru/021.html
②瀬戸本業窯
瀬戸は千数百年に亘り、良土の恵みを受け陶磁器が焼かれてきました。
純白で強度耐火度に優れた陶土は今だ当地の右に出るものがないと言われます。
1800年より磁器(新製焼)の生産が始まり、産業の源が築かれ、
近世に於いては輸出玩具(ノベルティー)、ニューセラミックスなど新しい分野へと展開しています。
しかし、瀬戸本業窯は、すべての窯業基盤となった鎌倉以来の伝統を伝える、本業焼きを守り続けて
います。
http://www.seto-hongyo.jp/
































